「鉄鋼業って、まだ未来があるの?」
そんな声を耳にすることが増えました。
たしかに自動化や環境対策の波の中で、
業界は大きな変化を迎えています。
私は現場で十数年働いてきましたが、
日々感じるのは“変化”と“可能性”です。
このブログでは、鉄鋼業のリアルな現場の声と、これからの働き方のヒントを、
私自身の経験を通じてお届けします。
溶接士として働く私の未来:鉄鋼業のこれからを考え

溶接士として現場に立ち続けてきた私が、
最近よく考えるのは「この仕事に未来はあるのか?」ということ。
AIやロボットの技術が進む中で、手作業の価値が問われる時代が来ています。
でも、現場で感じるのは、機械では
できない“人の技”がまだまだ求められて
いるという事実。
このブログでは、溶接士としての経験と、
これからの鉄鋼業界の行方について、
私なりの視点で語っていきます。
自動溶接でできること・できないこと。そして、手溶接の価値とは?

現場では自動溶接の導入が進み、省力化や作業の均一化が図られています。
確かに、自動溶接は大量生産や単純な直線溶接、同じ形状の繰り返し作業には強く、
スピードも安定性も優れています。
しかし、その反面「できないこと」もあります。
例えば、狭くてロボットアームが入らない場所、材料の歪みが大きい部分、複雑な
立体形状などは自動では対応が
難しく、プログラム通りにいかない状況
ではエラーが出やすいです。
さらに、異常時の判断や細かな調整は
人の経験に頼る部分が多いのが現実です。
そこで活きるのが手溶接の技術です。
手溶接は、現場の状況に応じて
溶接条件を即座に判断・調整でき、
どんなに入り組んだ場所でも対応できる
“対応力”があります。
また、熟練の技によるビードの美しさや強度は、まだまだ機械には真似できない
レベルです。
つまり、自動溶接と手溶接は「使い分け」が重要。
どちらか一方ではなく、両方の特性を理解し、補い合うことでより良い品質の仕事ができるのです。
🔧 建設業・溶接作業における人材不足の主な理由

① 若手の就職希望者が少ない
- 建設・製造業は「3K(きつい・汚い・危険)」
というイメージが強く、若者に敬遠されがちです。 - オフィスワーク志向の若者が増え、
現場系の仕事の魅力が伝わって
いない。
② 技術継承の断絶
- ベテラン溶接士の引退が進む中、
若手への技能継承が十分に行われていません。 - OJT(現場教育)だけでは限界が
あり、教える側も時間や余裕がない。
③ 賃金・待遇が見合っていない
- 技術や危険を伴う作業であるにもかかわらず、給与が他の業界に比べて
高くないケースも。 - 労働時間の不規則さや休日の
少なさも、敬遠される理由に。
④ 資格取得のハードル
- 建設現場で必要な溶接資格(JIS、アーク溶接など)は難易度が高く時間もお金もかかる。
- 未経験者にとっては「始めにくい」
業種となってしまっている。
⑤ 外国人労働者頼みの現場構造
- 技能実習制度などで
外国人労働者に依存する体制になっており、日本人の職人育成が後回しに。 - 言葉・文化の壁で教育に時間がかかることも人材不足を加速させている。
🔧 まとめ:建設業に明るい未来はあるのか?
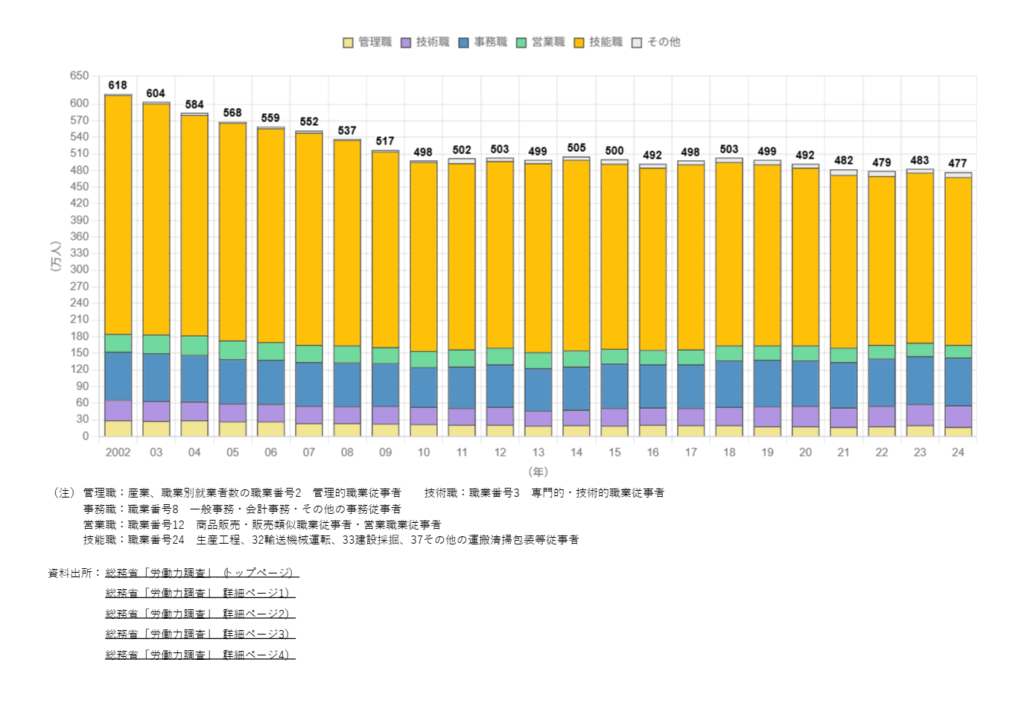
建設業は人材不足や高齢化といった
課題を抱えていますが、
同時に技術革新や働き方改革の
可能性も広がっています。
ロボット・自動化・ICT技術の導入に
より、作業の効率化や安全性の向上が期待され、若者や女性にも参入しやすい環境が整いつつあります。
これからの建設業は、技能とデジタルの
融合、そして人を育てる意識が不可欠です。
現場で働く人が「誇り」と「安心」を持てる職場づくりができれば、建設業には
十分、明るい未来があると私は思います。
この夏を乗り切るための熱中症対策
【ご安全に】







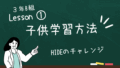

コメント